クロストークセッション

クロストークセッションでは、TIB Studentsのサポーター派遣を受けた学校の教員、生徒、そして講師を務めたサポーターから、アントレプレナーシップ教育を受講しての感想やその効果が共有されました。
登壇者は以下の通りです。
- 桜井 伸一氏(東京都立晴海総合高等学校)
- 別木 萌果氏・生徒の皆様(東京都立小川高等学校)
- 今井 朝子氏・生徒の皆様(自由ヶ丘学園高等学校)
- 藤本 あゆみ氏(一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事)
- 鈴木 彩衣音氏(株式会社SISTERS 代表取締役)
- 今井 善太郎氏(株式会社Classroom Adventure 共同創業者)
モデレーターは、TIB Students事務局の岡村が務めました。

トークセッションテーマ①:TIB Studentsとの出会い
– 本事業を活用された際の学校側としての思いについてお聞かせください。また、サポーターの皆さまは、どのような思いでこの取り組みに参加されているのか教えていただけますでしょうか。
桜井 伸一氏

当事業を活用したのは、コロナ禍が明け始めた頃です。
学校でもさまざまな取り組みが再開できるようになったタイミングでお声がけをいただきました。
本校の生徒は約8割が女子で、中学時代に十分な体験の機会を得られなかった生徒が多くいます。さらに、「大人」という存在を教師や保護者といった限られた価値観でしか知らず、どこか閉鎖的な考え方をもった生徒が多い印象を受けていました。
そこで、生徒に外の世界から刺激を与え、新しい価値観に触れさせたいと考え、TIB Studentsに参加することを決めました。
特に、実際に社会で活躍している女性の話を直接聞かせたいと思い、藤本様に登壇をお願いしました。授業後には、女子生徒だけでなく男子生徒も「こういうかっこいい大人の女性がいるんだ」と知り、自分たちも同じような道に進めるかもしれないと感じたようです。
この経験は生徒たちの進路観にも大きな影響を与えました。「進路をもう一度考え直したい」という声が増え、藤本様の講演をきっかけにチャレンジ精神が芽生えた生徒も現れました。
さらに、SusHi Tech Tokyo 2025に出展を決定した際は、生徒自らが企画を立て、「先生は口出ししないでほしい」と言うほど、自発的な動きが見られました。
こうした姿を目にし、私自身も大きな手応えを感じています。
藤本 あゆみ氏

桜井先生との事前の打ち合わせで、キャリアの可能性について話してほしいと依頼を受けました。
そこで、私自身のさまざまな経験や、海外で実際に起きているグローバルな状況を交えながらお話ししました。そうすることで、生徒さんたちが将来をもっと広い視点で考えられるきっかけになればと思ったんです。
別木 萌果氏

私は、政治経済を教える中で「教科書通りの経済の授業では、生徒が実感を持てない」と感じていました。そこで、思い切って「みんな社長になって、自分でビジネスプランを作って発表してみよう」という授業を企画したんです。
ただ私自身、大学を卒業してすぐに教員になったため、一般企業や会社設立についての具体的なイメージがあまりありませんでした。だからこそ生徒と一緒に学びたいという思いから、当事業に申し込みしたのがきっかけです。
担当する5クラスのうち3クラスでは鈴木さんをお招きし、残りの2クラスではボーダレス・ジャパンの「For Good」の小松さんにクラウドファンディングの授業をしていただきました。その結果、「クラウドファンディングで資金を集めて起業準備をしたい」と発表する生徒も現れ、私自身も大きな手応えを感じています。
また落とし物を貸し出すビジネスや、朝起きるのが苦手な小学生のための学校など、ソーシャルビジネスに近い多様なアイデアが生徒から出てきたことも印象的でした。ただ、利益の出し方に課題を感じる生徒も多く、その点は今後の学びのテーマになると感じています。
鈴木 彩衣音氏

私の授業では、ただビジネスの話をするだけではなく、自身の学生時代から社会起業家として取り組んできた経験をもとに、社会問題をビジネスで解決する方法やキャリアの考え方についてもお話ししました。
クイズ形式やディスカッションを交えて、生徒たちが自分で考え、意見を出せるように工夫しました。
自分が社会問題に関心を持つきっかけを話したことで、生徒さんの心に響いたのが分かったときは嬉しかったですね。
私の学生時代には、アントレプレナーシップや探求学習はまだ一般的ではなかったので、今の生徒さんたちには、そうした機会をできるだけ多く提供したいという思いがあります。
小川高校の生徒の皆様
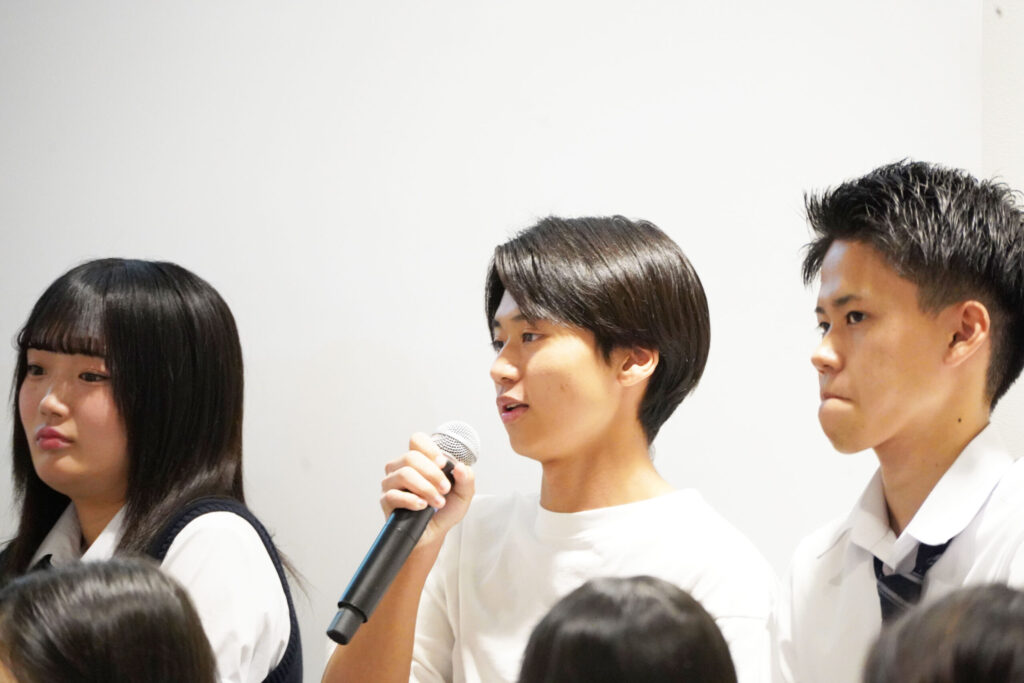
普段の授業ではなかなか触れられない、ジェンダーや貧困について学び、新しい視点を得ることができました。特に印象に残っているのは、鈴木さんが夢に向かって努力し、困難に直面しても諦めない姿です。
その強さに心を打たれ、私もこんなふうに前へ進みたいと思うようになりました。
さらに、日本に生まれることが当たり前ではないという事実にも気づかされました。世界には貧困や紛争に苦しむ国がある中で、日本で不自由なく暮らせている自分がどれほど恵まれているかを深く実感しました。
日本での“当たり前”が世界では特別なことだと再認識し、差別や貧困といった課題に、これまで以上に意識を向けていきたいと思います。
今井 朝子氏

私はアメリカの大学に通っていたのですが、そこでは周りが起業するのは当たり前という環境でした。一方、日本では起業を志す人はまだ少なく、そうした話を直接聞ける機会もほとんどありません。
それでも、将来は日本でもそうした道を選ぶ生徒がもっと増えるはずだと感じていました。だからこそ、その環境や考え方をぜひ伝えたいと思ったんです。
私の授業では、生徒が自分のコアバリュー(大切にしたい価値観)を軸にプロジェクトを立ち上げる取り組みを行っています。ただ、身近な年齢で実際に経営をしている人を見つけるのはなかなか難しかったんです。
そんな中で当事業の存在を知り、今井善太郎さんにお願いできたことは、生徒にとっても私にとっても非常に価値のある機会になりました。
授業後の生徒たちは、自分の価値観をもとにプロジェクトを立ち上げる段階に入っていて、予想以上に多くの学びを得られていると感じています。
今井 善太郎氏

まずは、私が制作したゲーム『レイの失踪』を生徒のみなさんに体験してもらいました。このゲームは、闇バイトを追体験することで情報リテラシーを楽しく学べるというものです。
SNSの使い方や闇バイトの危険性など、本当は重要だけれど“つまらない”と思われがちなテーマを、ゲームを通して疑似体験しながら学べるようにしています。
もともと私は意識の高い起業家というわけではありませんでした。会社を設立したのも、お金の契約が煩雑だったので法人化したにすぎません。生徒への話は、どうしても“やりたいことがある”という前提で進みがちですが、実際にはその“やりたいことを見つける”こと自体が難しいと思っています。
私自身、カナダの田舎の高校で3年間、毎日4時間散歩をする生活の中で、自分のやりたいことを見つけました。だからこそ、忙しくしすぎず、自分と向き合う時間を持つことの大切さを伝えたいんです。
自由ヶ丘学園高等学校の生徒の皆様

ゲームを仲間と一緒に作っているお話を聞いたり画像で見たりすることで、“仕事って意外と楽しいものなんじゃないか”と思えるようになりました。
また、散歩の話がすごく印象に残りました。普段の生活では考える時間がほとんどないことに気づきましたし、これからはゆっくり考える時間を作って、社会に貢献できるようなことをしていきたいです。
トークセッションテーマ②:将来のありたい自分と行動
– サポーター派遣を通して、先生方やサポーターの皆様には、生徒さんに対し「どんな行動や考え方を持つと良いか」ということについて教えてください。また生徒さんの場合であれば「どういうふうに自分の心持ちが変わったか」という点を教えていただけますでしょうか。
今井 朝子氏

生徒たちに「大人になるって楽しいな」と感じ、自分で自由に考え、それを自分の力で実現できることを知ってもらえれば良いなと思います。
多くの大人が生徒たちを助けようとしていることを理解し、「自分の持っていること何でも言って提案して一緒に活動していいんだ」と分かってくれることを期待しています。
自由ヶ丘学園高等学校の生徒の皆様

今井善太郎さんの話を聞いて考え方が変わりました。高校生でも様々なことを考えて実践することで社会貢献や人助けができると分かり、自分でも積極的に行動していきたいと思います。
実際に友人と散歩をして、自分に何ができるのかということを考えながらできたことはいい経験になったと感じています。
今後は高校生だからと受け身にならず、「高校生だからこその視点」で自発的に行動したいです。
今井 善太郎氏

現代は多くの支援者やAIの力によって、アイデアを形にするのが非常にスムーズになってきています。
これまでよりも10倍のスピードで物が作れ、人も少なくてもよいため「どういう課題を解決したいか」や「どういう生き方をしていきたいか」といった根源的な問いに向き合うことが大切だと思います。
別木 萌果氏

生徒たちには、さらに視野を広げて、積極性を身につけてほしいと考えています。
サポーターを学校に派遣していただいたことで、私自身も2つの課題に気づきました。1つ目は、サポーターのお話を聞いて“自分もなりたい”と前向きに感じる生徒がいる一方で、“自分には難しい”と感じる生徒も一定数いたのではないかということです。
2つ目は、知識や思考力はテストやレポートで評価できますが、主体性やチャレンジ精神といった資質は評価が難しく、短期間では成果が見えにくいということも改めて感じました。
それでも、この取り組みがきっかけとなって、生徒一人ひとりが自分なりのペースで視野を広げ、次の行動につなげてくれれば嬉しいですね。
東京都立小川高等学校の生徒の皆様
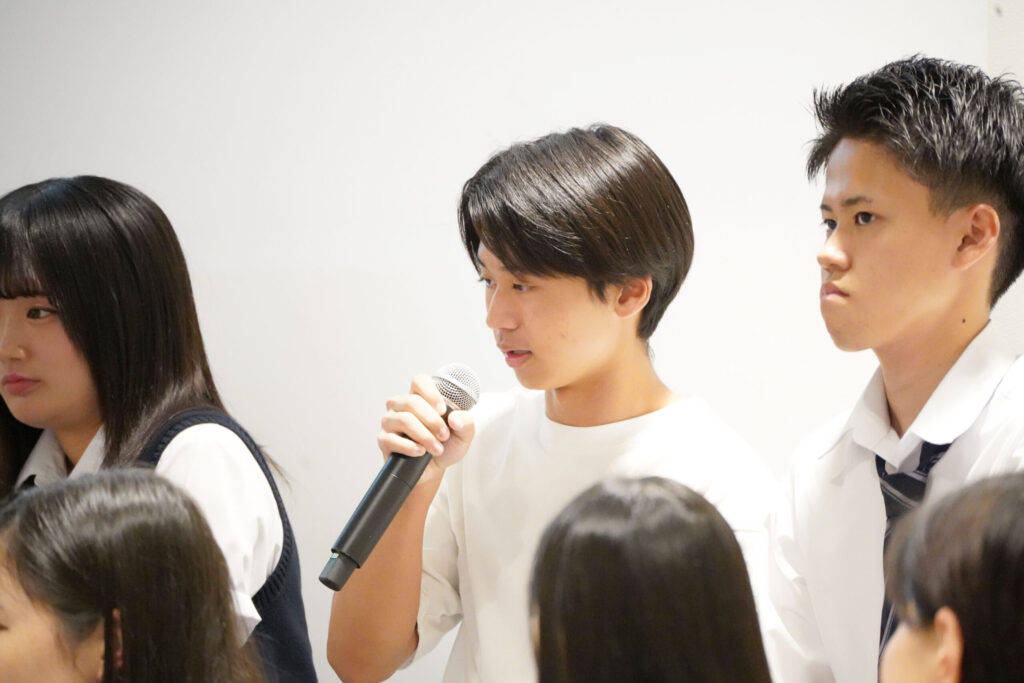
起業というものは、これまで自分には遠い存在だと思っていました。でも、今回のお話を聞いて、もっと身近なこととして考えられるようになりました。
そして、我々若い世代が社会問題を正面から受け止め、様々なことにチャレンジしていきたいという気持ちが芽生えました。
鈴木 彩衣音氏

今回の授業で一番伝えたかったのは、「もっと将来を自由に考えていいんだよ」ということです。
私が学生だった頃は、社会起業や学生起業という言葉もまだ浸透していませんでした。現代はAIの登場などもあって、10年後には“名前のない職業”が相当数生まれていると思います。
だからこそ、生徒のみなさんには安定志向だけにとらわれず、自分がワクワクする気持ちや、挑戦してみたいという思いを大切にしてほしいですね。
桜井 伸一氏

生徒たちには、日常生活が楽しく大人になることが楽しみだと思ってもらえるようになってほしいです。
藤本様の講演後、多くの生徒が「藤本さん、かっこいい」と感想を述べ、社会人のイメージが変わったようでした。「自分も面白いことをやってみたい」という意見も、生徒から出てきたことはとてもうれしかったですね。
東京には、TOKYO STARTUP GATEWAYへの応募や、日本政策金融公庫の高校生ビジネスプラングランプリ優勝者との交流など、豊富な教育資源があります。また、生徒たちがSusHi Tech Tokyo 2025のイベントに参加した際に、英語力や異文化コミュニケーションの重要性を痛感したことや、来場された方々からのアドバイスをとても貴重に感じていたことも印象的でした。
このような恵まれた環境を活かして、生徒たちが挑戦を楽しめるように今後も支援していきたいです。
藤本 あゆみ氏

アントレプレナーシップは、起業家になることだけを意味するのではなく、新しいものを次の世代に紡いでいく人だとイメージしています。
学生のみなさんには、会社を設立することをあくまでひとつの選択肢として捉えつつ、多様なサポートがそろっている東京の強みをぜひ活かしてほしいですね。
また、私はインプットの重要性が非常に高いと考えています。“being(自分が何を大切にするか)”を育むためには、学校の外や異なる学年の人との交流など、さまざまな経験を通して引き出しを増やしてほしいと思っています。
