パネルディスカッション – アントレプレナーシップ教育に対する考え方
第二セッションでは、さまざまな立場でアントレプレナーシップ教育に携わる5名の登壇者によるパネルディスカッションが行われました。
- 池田 巧氏(東京電機大学中学校・高等学校 専任教諭)
- 宮田 明子氏(東京都立国立高等学校 校長)
- 跡部 悠未氏(東京農工大学 ディープテック産業開発機構 准教授)
- 山口 文洋氏(株式会社ベネッセコーポレーション 取締役副社長 執行役員 兼 CPO)
- 菅田 悠介氏(NPO法人MOTTAI 代表理事)
モデレーターを務めたのは、元テレビ東京アナウンサーの須黒清華氏です。

ディスカッションでは、それぞれの立場から現在の取り組みを紹介するとともに、アントレプレナーシップ教育に対する考え方や課題意識について多角的な意見が交わされました。
未来について考えよう:若者にはどのような機会が必要か

– 教育現場においてどういった機会を学生に与えることで今後の活躍につながっていくのでしょうか?
池田氏

私は、継続できる環境の提供が重要だと考えています。継続を支える要素は大きく二つあります。
一つ目は、その人を応援する仲間の存在です。
ここで重要となるのがアントレプレナーシップという考え方です。本人の意欲が高くても、周囲に仲間がいなければ孤立しやすくなります。そのため、継続するためには、周囲のサポートや仲間の存在が不可欠となります。
二つ目は、大人の関わり方。
幼少期に砂場遊びに夢中になるように、本来、人間は何かを継続したいという強い意欲を持っています。しかし、成長する過程で大人から「もうやめなさい」「勉強しなさい」「時間がない」などと否定的な言葉を受けることにより、その気持ちが失われがちです。
だからこそ、大人や仲間が意識的に継続できる環境や機会を整えることが大切だと思います。
本校では、生徒から「このプランに参加したい」「このコンテストに出たい」などの相談があれば、「やってみよう」と全面的に支援する体制を構築しており、生徒たちが安心して挑戦できる環境を提供しています。
宮田氏

生徒の主体性を引き出す環境作りが必要だと思います。
以前、生徒が地域の桜並木保護活動に参加した際、最初は単なるボランティアとしての参加でしたが、徐々に自分たちでも何かできるのではないかと考えるようになりました。この経験が、その後の様々なコンテストや活動への参加につながるきっかけとなりました。
生徒が「何かをしたい」と思ったときに、「こういった機会がある」「こんな方法もある」と教員側から提示できる準備が必要です。アントレプレナーシップは直接的に教え込むことが難しいため、教員自身が多様な情報や選択肢を持ち、生徒の考えを引き出せるよう備えることが重要です。
そのため教員は、「何を教えるか」よりも「どのように生徒の考えを引き出すか」という視点が求められます。
実施すべきことはたくさんある中で、非常に大変な部分はありますが、生徒一人ひとりの興味関心や可能性に丁寧に寄り添い、好きなことを発見して深められる環境を整えることが重要な課題です。
跡部氏

東京農工大学には農学部と工学部があり、大学内に「テックガレージ」という施設を新設しました。
これは起業に関心がある学生向けのコワーキングスペースと、ものづくり工房が併設された施設です。ものづくりと起業に関して、それぞれ教員が相談窓口を週1〜2日開設し、自由に相談に来れる時間をつくっています。
施設開設当初は、ものづくり工房の利用は盛んでしたが、起業相談に訪れる学生は少数でした。しかし、継続的に活動を行う中で、学生が好きなものを自由に制作し、発表機会を通じて他者から評価を得るようになると、「自分の制作物が評価され、他者に影響を与えている」という実感を持つようになりました。
次第に学生は、「活動を継続する方法」「より多くの人に使ってもらう方法」などを自発的に考えるようになり、起業相談にも訪れるようになりました。「ビジネスとしての展開方法」「企業との連携方法」「収益化の可能性」など具体的な相談が増えています。
重要なのは、学生たちは初めからアントレプレナーシップの意識を持っていたわけではなく、好きなことに取り組んだ結果、自然に次のステップへ進みたいという意欲が生まれたことです。このように、自覚や意欲が自然と芽生える環境を提供することが重要です。
山口氏

若者に必要な機会とは、大人が良かれと思って一方的に用意したものではなく、「余白の時間」を与えることだと考えます。
子どもや社員を思って大人が過度に配慮したり計画したりするのではなく、自由に考える時間と空間を与えることが大切なのではないでしょうか。
私は田舎育ちなのですが、子どもの頃は詰め込み教育や受験とは無縁でした。
遊ぶためのおもちゃも限られている中で、その日の天候や人数、遊ぶ場所などを踏まえて自分たちでルールや遊び方を考えました。まずは実践し、「今日はめちゃくちゃ盛り上がったね」あるいは「面白くなかったね」ということを繰り返していたんです。
この経験は企業や組織でも通じるものがあります。時間に余裕を持ち、自由な発想でブレストを行うことで、事業やサービスの改善案が自然と生まれます。
そして何より、失敗を恐れずに実践できる環境を整えることが必要です。失敗は恐れるべきものではなく、重要な学びの機会です。
菅田氏
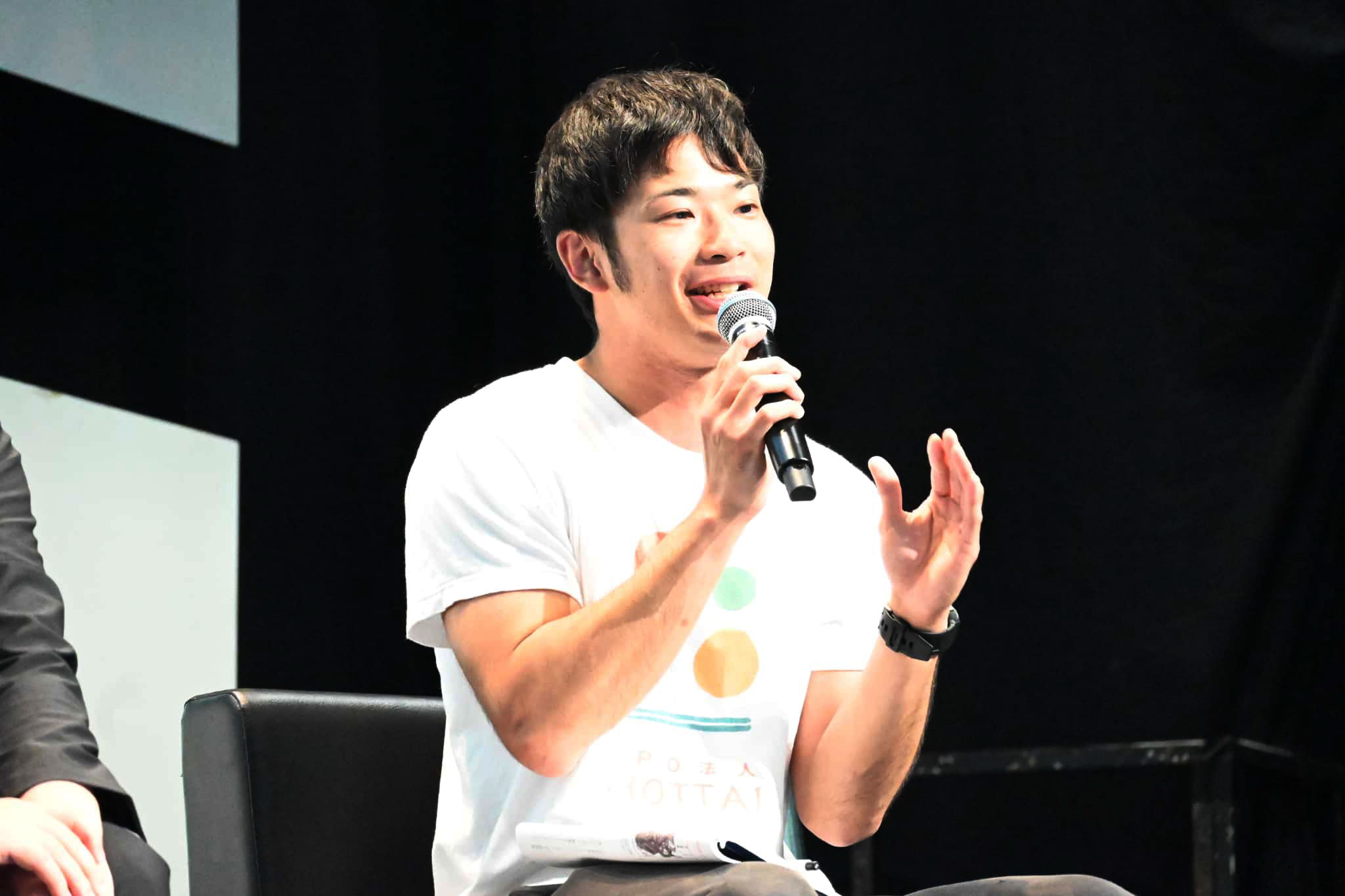
過去にTIB Studentsで、中高生向けに話をする機会を3回いただきました。その際に心がけていたのは、中高生にとって身近な存在であることと、「自分でもできるかもしれない」と感じてもらうことでした。
生徒にやりたいことを見つけてもらうために、「好きなことを仕事にしよう」「好きなことを見つけよう」という話が今日では多いように思いますが、僕は逆に「嫌いなことって何だろう」ということを考えてもらいます。
好きなことは変わる可能性がありますが、生理的に受け入れがたいことは変わりにくいものです。だからこそ、嫌いなことを解決することで持続力が自然と身につくのではないかと考えています。
中高生にとっては「こんなやり方もあるんだ」「自分でもできるかも」という感覚になってもらうことを大事にしています。
須黒氏

皆さまのお話を伺い、先生方によるサポートの重要性はもちろんのこと、学生自身が自ら考えるための余白の時間をいかに確保するかが、これからの教育における鍵になるのではと感じました。
現代の子どもたちは非常に多忙な毎日を送っていますが、その中で自分と向き合い、内省する時間や自由な発想を育む余白をいかに提供できるかが、今後ますます求められていくのではないでしょうか。
学生が自ら考える環境を作り上げるためには

– 学生が自ら考える環境を作るためには、どのようなことが学校側には求められるのでしょうか?
池田氏
幼い頃に好きなことに自由に取り組む経験は、子どもたちの原点になると考えます。好きなことを夢中で追求した体験が、大人になったときに新しいことへ挑戦する原動力につながるのではないでしょうか。
一方で、今回のお話を通じて、学校現場が見直すべき課題も浮かび上がりました。教師が生徒のためを思って指導することが、時として無意識のうちに生徒の可能性を制限してしまうのではないか、私たち教員が子どもたちの可能性を潰してしまっているのではないかということを改めて考えさせられました。
宮田氏
学生が自ら考える環境を整えるためには学校側に、さきほど山口氏が仰っていたような「余白の時間」 を作る工夫が求められます。しかし、実際に余白の時間を確保するのは簡単ではありません。
学校の勉強にゆとりを持たせようとしても、その時間が塾や習い事、スマホの使用などですぐに埋まってしまうケースが多くあります。
生徒自身がどういうことをやりたくて、どういう風になりたいのかを考える内省の時間を確保するのは、学校現場でも悩ましいところです。我が校では進学を考えている生徒が多いので、勉強しなくてはという意識の生徒が非常に多く、そのあたりのバランスは本当に難しい課題ですね。
山口氏
完全に自由にはできない部分があるため、バランスが大切だと思います。
親として提供したい環境、学校が用意したい環境という二つの視点の中で、あれもこれもという状況から少し断捨離し、「これはやってほしいけど、こちらは余白にしよう」と意識的に決めることが必要ではないでしょうか。
ただ、その際に気をつけるべきことは、余白の時間がスマホやYouTubeを眺めて一方的に情報を受け取るだけにならないことです。
好きなことでも構わないので、自分で情報を収集し、考えて実践してみる。そのような成功や失敗の体験を積む機会を提供することが大切です。
学校の教育環境は徐々に良い方向に変わってきていると感じます。「正解は一つではない」「相対的な評価を行う」といった視点が取り入れられ、一人ひとりの個性や特性を活かしたり褒めたりする機会も増えています。
詰め込み型ではなく、探究学習を通じて「みんなで問いを探そう」「正解のない問題について一緒に考えよう」という取り組みが小中高の現場で広がりつつありますので、こうした取り組みがさらに広がれば、子どもたちがさらに楽しみ、夢中になれる時間や空間が生まれ、新しいタイプの社会人が育っていくのではないでしょうか。
宮田氏
学校は基本的に、国語や社会といった教科ごとに教員を採用するため、アントレプレナーシップ教育の専門教員はいません。そのため、各教科内でどのようにアントレプレナーシップ教育を取り入れるべきか、教員自身が分からない状況です。
逆に、生徒の方が柔軟な発想力や創造力を持っていることもあります。そのような生徒の力を潰さないよう、学校側は意識や体制を整える必要があるのではないでしょうか。
現在、学習指導要領に則って教育内容が変わりつつあり、各教科の評価基準も変化しています。このように、社会の変化に対して少し遅れをとりつつも、学校現場が着実に変わってきていることは間違いないでしょう。
須黒氏
仲間内で対話を重ね、互いの意見を尊重しながら同じ方向に向かって進むような、相手を否定しない教育の在り方が、今後ますます重要になってくると感じました。
そのような変化を受けて、学校現場における生徒の評価軸も、従来の「正解・不正解」から、協働性や主体性、多様な価値観への理解といった観点へと、徐々にシフトしていくことが期待されます。
いまできることを考えよう:教育現場をどのように変えていくべきか

– 徐々に変化をみせている教育環境ですが、現状はアントレプレナーシップを教えられる先生も少なく忙しい状況です。アントレプレナーシップを醸成するために、教育現場はどのような行動が必要なのでしょうか?
池田氏

私は、教員と生徒が「問いを立て続けることの価値」を共有することが極めて重要だと考えます。
探究教育では、正解のない問題に対して生徒自身が問いを設定し、仮説を検証していきます。ところが、私たち教員は日常の授業で「これが正解」「これが不正解」「これは正しい」「これは間違っている」という評価を繰り返しています。そのため、教員と生徒の間で問いに対する認識がずれることがあります。
だからこそ、教員も生徒も問いを立て続けることが持つ重要性を理解し、それがアントレプレナーシップや新しい価値創造につながることを教育現場全体で共有する必要があると思っています。
私自身も一般社団法人アントレ教員ラボを設立し、教員向けのアントレプレナーシップ教育を推進しています。多くの教員と協力し、これからの教育現場をより活性化していければと考えています。
跡部氏

深く掘り下げて得た知識やスキルをどのように活用するかという課題があります。特に大学は、似通った属性の人たちで構成された濃密なコミュニティが形成される傾向にあり、専門的な研究には適していますが、視野が狭くなりがちです。
そのため、普段所属しているコミュニティ以外との交流が非常に重要になると考えています。異なる分野の研究者や、研究者以外の人、異なる世代、国籍、性別など、多様な人々とどれだけ交流できるかが鍵となるでしょう。
様々な世代の人から学べることはもちろんですが、特に学生を見ていると、同世代でありながら自分とは全く異なる立場で活躍する人たちに出会った時、大きな刺激を受けているんです。
私たち教職員は学生に「失敗を恐れずに挑戦しろ」と日常的に伝えていますが、一方で自分たちは仕事上での失敗が許されない環境にいます。このような状況で教職員自身が変わらずに、学生に挑戦を促しても説得力は薄れてしまいますよね。
だからこそ、学生が積極的に挑戦し、その過程で成長していく姿を間近で見ることが教職員自身にも変化を促します。学生の変化を起点として教職員も「自分たちも変わらなければいけない」という意識を持ち、その考えを少しずつ周囲へ広げていくことが大事だと思っています。
菅田氏

私は外部人材を積極的に活用すべきだと考えています。
生徒にとって最も身近な大人は、先生や親の存在です。そのため、普段は接点のない方々と交流することで、同じ言葉でも新鮮な受け止め方が生まれることがあります。私自身も学生と対話をする中で、「言葉が響きました」という反応をいただくことが多く、こうした外部との接点が大切だと感じています。
私の自宅近くのある学校では、地元の農家を講師として招き農業体験を実施している事例があります。生徒たちからは、「農業って面白い」「近所にこんな人がいるんだ」という声が上がり、中には実際にその農園で卒業後に働きたいと希望する生徒もいるほどです。
先生が教えられることには限界があります。だからこそ、先生や親以外の外部人材に協力を仰ぐことが必要なのです。外部から人を招くことで、生徒は「当たり前だと思っていたことが実は違った」「身近な場所にも面白いことがある」と気づく機会を得られます。
当たり前を疑い始めることで、生徒自身が変わり、教員も変化を促されます。時には、生徒が教員に新しい視点を提供するという逆転現象も生まれ、教育現場に良い循環をもたらすことができるのではないでしょうか。
宮田氏

私は、世界との接点を増やすことが大切だと考えています。
日本と海外の違いは当然ながらあるわけですが、海外研修などの取り組みを通じて、そうした違いに気付いて新しい視点で自分の考え方を再構築したり、今までには気付かなかった視点で身の回りの世界を眺め直すことが出来たりします。実際に研修やアントレプレナーシップの発表会に参加した生徒たちは、意識や行動が明らかに変わっているんです
そんな生徒たちの変化を見ていると、次第に大人の意識も変わります。これが良い相乗効果を生んでおり、私たちは生徒から学ぶことが多くあると感じています。
まだ何も決まっていない原石のような生徒たちから得られる学びは非常に多く、大人は失敗を恐れたり、社会的な立場を気にして発言を控えたりしがちです。しかし、生徒たちはそのようなことを気にせず自由に挑戦する姿勢から学ぶことは本当に多いのです。
山口氏

学校とはどのような場であるかを考えたとき、アントレプレナーシップそのものを最優先で育てる場所というより、むしろ社会に出る前の予行演習の場と捉えています。
社会には多様な人々が存在し、その中で自分の立ち位置を見つけ、自らの価値を発揮して貢献することが必要です。
学校も同様で、個性豊かな友人たちとの交流を通じて「自分とはどういう人間か」を内省し、コーチングによって自己理解を深める場であることが理想だと思います。
ただ、今後の社会を見据えたときに重要となる視点があります。私自身、イノベーションを起こしてきた企業に勤めておりますが、イノベーションが生まれる原動力を振り返ると、それは「チーム力」だと気づきました。
例えばサッカーでは、フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーなど、異なる専門性を持ったメンバーが集まるからこそ、一人では成し得ないイノベーションが起こせるわけです。
だからこそ学校現場でも、生徒自身が自分の好きなことや得意なことを具体的に認識し、それを抽象的な理解へとつなげられるよう、先生方が積極的にコーチングし認知させていくことが大切なのではないでしょうか。
須黒氏

先生方はもちろんのこと、私たち保護者もまた、子どもたちの前で失敗を恐れず、その経験を共に学びに変えていく姿勢が求められるのでしょう。
大人自身が変化を受け入れ、挑戦する姿を見せることが、子どもたちの挑戦を後押しする大きな力になるはずです。
パネルディスカッションを通しての登壇者からの感想

– 最後にパネルディスカッションを通しての感想を一言ずつお願いします。
菅田氏
失敗を新たな学びの機会として前向きに捉える大切さを再確認しました。若者の意識を変革するためにも、「当たり前」を疑い、挑戦する機会を提供する必要があると感じました。
山口氏
理想と現実のギャップを埋めるために、大人が子どもに対する過度な期待を再評価し、余白と信頼を与える姿勢が必要であると思います。
跡部氏
理系大学の専門性を活かしつつ、多様な分野や人々と連携することがアントレプレナーシップ教育には欠かせません。少しでも興味がある方々と一緒に盛り上げていきたいです。
宮田氏
総合的な探究の時間を効果的に活用し、生徒それぞれの個性や興味・関心を伸ばしていく教育が求められています。学校現場での積極的な取り組みを通じて、日本の未来を担う人材育成に貢献できればと思います。
池田氏
教員自身が変化を恐れず新たな挑戦を続けることが重要です。それがアントレプレナーシップ教育の浸透につながり、生徒だけでなく教員の意識改革も促進されると実感しました。
イベントを通して育まれるアントレプレナーシップの可能性
「未来をつなぐアントレプレナーシップ教育 公開授業&パネルディスカッション」は、アントレプレナーシップを単なるビジネススキルとしてではなく、生涯を通じて求められる「生きる力」として捉え直す機会となりました。その意義を、あらためて見つめ直す場でもあったといえるでしょう。
異なるバックグラウンドを持つ登壇者たちによる熱のこもった意見交換を通じて、私たちが直面する課題や、未来への新たな可能性が浮かび上がりました。若い世代はもちろんのこと、多くの参加者にとっても、大きな気づきと学びのあるひとときとなりました。
今回のイベントが一つの起点となり、より多くの方が自身の可能性を信じ、失敗を恐れず挑戦できる社会づくりが進むことが期待されます。
